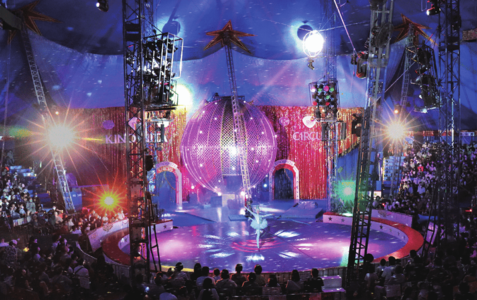「大自然じゃなくてもいい」NPO法人国際自然大学校に学ぶ、日常で育つ"子どもの力"

大自然の中での体験は、子どもがぐんと伸びる機会ですが、それだけがすべてではありません。
通学路の木々、夕方の散歩道、ちょっとした料理のお手伝い----そんな身近な体験の中にも、成長の種は隠れています。
本部事務局を狛江に構え、40年以上にわたり自然体験を通じて「感じ・考え・行動する力」を育んできたNPO法人国際自然大学校。今回は本部事務局マネージャー・関口千尋さんに、家庭でも実践できる"子どもが伸びる工夫"と、成長を促すための親子のちょうどいい距離感について伺いました。
アウトフィッターを育てる、自然から学ぶ人づくり

木々のざわめき、川の流れ、仲間と過ごす時間。
自然の中での体験は、一度きりの思い出にとどまらず、その後の人生を照らし続けます。
国際自然大学校は、子どもから大人まで世代や場面に応じた多彩なプログラムを展開し、自然体験を通じて「前向きに生きる力」を育んできました。活動の中心にあるのが「アウトフィッター」の育成です。
アウトフィッターという言葉は、創設者の佐藤初雄と桜井義維英の造語で、"自然や人との関わりの中で人生を前向きに生きている人"のこと。ただ自然の中で遊ぶのではなく、体験を通して人として成長していくことを目指しています。それこそが私たちの原点であり、大切にしてきた想いです(NPO法人国際自然大学校 本部事務局マネージャー 関口千尋さん、以下同)
子どもたちの成長を支える2本の柱

国際自然大学校の子ども向けプログラムは、大きく「通年型」と「シーズンキャンプ」に分かれています。
通年型は毎年5月に始まり、翌年2〜3月まで、約10〜11か月かけてじっくり取り組みます。子どもたちは決まった班の仲間と1年間を通して活動し、同じスタッフが伴走する仕組みです。短期のキャンプではその場かぎりの出会いになりがちですが、ここでは顔なじみの仲間やスタッフと共に時間を重ねることで、絆が深まり、関係性の質もぐっと高まっていきます。スタッフは子ども一人ひとりの変化をしっかり見守れるため、その成長を具体的に保護者へ伝えられるのも大きな特徴です
通年型プログラムの締めくくりには、ウォーキングが待っています。コースごとに距離は異なり、最短で5kmから、長いものでは夜を越えて30km以上歩く『オーバーナイトチャレンジハイク』に挑戦することも。

達成感とともに、一歩一歩を積み重ねる経験が
子どもたちの成長につながっていきます
もう一つの柱が、夏休みや冬休みなど長期休みに行うシーズンキャンプです。
1泊2日から最長4泊5日まで、伊豆や山梨、長野といった自然豊かなフィールドで展開されます。夏は川遊びや登山、冬はスキーや雪遊びなど、四季ごとの自然をテーマにしたプログラムが盛りだくさん。大自然に挑むダイナミックな体験はもちろん、初心者向けには親子で一緒に参加できるプログラムもあり、アウトドアが初めての方でも安心です
家庭や学校に戻ってから見える子どもたちの変化

自然体験をした子どもたちは、家庭や学校に戻ったあと、その行動や意識にさまざまな変化が表れるといいます。 たとえば、宿泊型キャンプで経験した配膳や片付け、寝具の準備といった役割が日常生活にもつながり、家でも言われる前にお手伝いができるようになる子が増えるそうです。
学校向けのプログラムでは、林間学校や移動教室の際にスタッフが主体となってコミュニケーションワークを実施しています。ゲームを通じて困難を乗り越える体験をすると、子どもたちのコミュニケーションが活発になっていきます。中には、それまで人の話を聞かなかった我の強いお子さんが、きちんと耳を傾けられるようになる場面もあるんです。そうした変化は、先生方とのふりかえりでもよく共有されます
さらに、食の面でも挑戦が広がります。
キャンプでは地元の野菜なども食事に取り入れますが、普段なら"嫌い"と言って手をつけない子も、仲間が食べている姿に背中を押されて思わず口にしてみることがあります。『食べてみたら意外とおいしかった』と苦手を克服できることも多く、これぞ"キャンプマジック"ですね
また、すぐには成果が見えなくても、体験が時間差で効いてくることもあります。
幼稚園の頃にキャンプで大泣きしていた子が、小学校高学年になって再会したときには、すっかり立派に成長していたんです。その姿を見て、体験の力はその場限りではなく、あとから確かに子どもを支えるものになると強く実感しました
子どもの小さなサインを見逃さない、スタッフのまなざし

国際自然大学校のスタッフが子どもたちと接するときに大切にしているのは、「見守る」と「目を離さない」の両立だそうです。
"見守る"というのは、手や口を出しすぎずに子どもの主体性を大切にすること。やりたい気持ちや前向きな挑戦を邪魔しないようにします。一方で"目を離さない"というのは、放っておかないということです。下を向いていたり、固い表情をしていたりするお子さんの小さなサインを見落とさず、必要なときには寄り添います
また、「失敗してもいい」という空気をつくることも大事にしているそうです。
最近の子どもたちは"失敗しちゃいけない"と萎縮しがち。だからこそスタッフは、そっと背中を押して、『やってみよう』と寄り添います
安全面では、活動を始める前に「セーフティートーク」と呼ばれる声かけを行い、その活動に潜む危険や気をつける点を子どもたちに伝えているそうです。
ただし、あれこれ言いすぎてしまうと体験を楽しめなくなってしまいます。だからこそ、年齢や特性に合わせて必要なことだけをシンプルに伝え、環境そのものを工夫して危険を避けるというバランスを大切にしています
ありのままを受け止めて、一人ひとりが輝ける場所に

国際自然大学校では、不登校の子どもや発達特性のある子どもも、その子らしさを自然に受け入れることを大切にしています。
子どもはとても敏感なので、"特別扱いされている"と感じると、自分も周りも居心地が悪くなってしまいます。だからこそ、ありのままを受け止め、安心できる関係性をつくることを意識しています
一方で、安全に過ごせるように必要なサポートも欠かしません。
すぐに走り出してしまうお子さんにはスタッフが寄り添い、トラブルになりそうなときは環境を整えるなど、一人ひとりが安心して挑戦できるよう工夫しています。大事なのは、"特別扱いすること"ではなく、その子の個性をそのまま尊重すること。そのうえで、一人ひとりがのびのびと楽しめるように、必要なサポートをそっと添えることなんです
家庭でもできる!
自然体験の学びを暮らしに取り入れる4つの工夫

「感じ・考え・行動する力」を育む国際自然大学校での学びは、家庭でも取り入れられます。
1.まずは体験、その後のふりかえりがカギ
大事なのは"危ないからダメ"と止めるのではなく、実際にやってみることです。包丁や火を扱う前に"セーフティートーク"で気をつけるポイントを伝え、あとは体験させてみる。そして必ずふりかえる時間を持つこと。キャンプでも"やりっぱなし"にはせず、ふりかえりを通して次の行動につながるきっかけをつくっています
2.見守る姿勢と"過度な期待をしない"こと
親子という関係はどうしてもお互いに甘えが出やすく、つい口を出したり介入してしまいがちです。だからこそ、ぐっとこらえて見守ること。そして"もっとできるはず"と期待をかけすぎないことも大切です。お子さんが小さな挑戦を積み重ねていけるように、寄り添いながら支えてあげるのがいいと思います
3.日常生活の中で 自然とつながる
自然体験で得られる気づきは、普段の生活のなかでも感じることができます。たとえば都会でも、道端の植栽や公園の木々は季節ごとに変化していますし、足もとには草花が芽吹いてきます。そうした小さな自然に目を向けながら散歩するだけでも立派な体験です。散歩から帰ったあとに『今日はどんな発見があった?』と親子で共有するだけで、学びにつながります
4.デジタルを味方に自然を深掘り
散歩中に気になった木や花を見つけたら、Googleレンズなどのアプリを使って調べてみるのもおすすめです。名前がわかると不思議とその植物に親しみが湧き、もっと知りたいという気持ちにつながります。自然と対極にあるデジタルも、自然をより深く知る『入り口』になるのです
「乗り気じゃない」をどう受け止める?
成長につながるヒント

せっかくの体験でも、子どもが「行きたくない」「やりたくない」と言うことがあります。そんなとき大切なのは、理由を見出すことだと関口さんは言います。
甘えや不安が理由なら、無理に親が引っ張るのではなく、信頼できる大人に預けて"小さく挑戦"させるのが効果的です。ほんの一歩でも成功体験になれば、その後につながっていきます
一方で、親との時間が足りないことが理由であれば、体験を増やすよりも親子で過ごす時間を大切にすることが必要です。
親との関係が十分に満たされていないと、せっかくの体験も子どもの心に届きにくいことがあります。だからこそ、あえて体験の数を減らしてでも、親子でゆっくり過ごす時間を確保することが大切なんです
高学年・中高生からでも遅くない、自然体験の意義

また、国際自然大学校での自然体験は、始める時期が遅くても心配はいりません。
小学校高学年や中高生からの参加でも十分に意味があります。この年代は感受性がぐっと豊かになり、思春期の入口でさまざまな壁にぶつかる時期でもあります。自分の気持ちに正直になれなかったり、人の目を気にして殻に閉じこもってしまうことも少なくありません。だからこそ、日常とは違う環境での体験が心を解きほぐし、殻を破るきっかけになるのです
さらに関口さんは、中高生の意義についてもこう語ります。
学校生活のなかで人間関係に悩んでいる子でも、キャンプは"普段と違う自分"を出せる場になります。ときには安心できる逃げ場にもなるんです。そして高校生になれば、ボランティアとして小さな子どもたちを支える機会もあります。普段は同世代の前では遠慮がちでも、小さい子と接するなかで"誰かの役に立てた"という実感を得られ、自分の良さを発揮できるんです
つまり自然体験は、年齢や状況にかかわらず、一人ひとりの心に"次の一歩"を踏み出す力を届けてくれる場なのです。 最後に、関口さんは保護者への思いをこう語ってくださいました。
学ばせようと肩ひじを張る必要はありません。まずは保護者ご自身が自然の場に出て、感じてみることが大切です。本当は、親子一緒に自然を楽しめることが理想。そのために親子で参加できるプログラムも用意していますので、気軽に体験してみてください

自然体験は、大自然の中だけでなく、日常の小さな場面にもあふれています。大切なのは、子どもが安心して挑戦できる環境を整え、そっと背中を押してあげること。国際自然大学校の取り組みから学べるのは、"特別な場所に行かなくても、子どもはぐんと伸びる"ということです。今日の散歩道や食卓でのひとコマが、未来を照らす一歩になるかもしれません。
【NPO法人 国際自然大学校】
主催・受託・指定管理の3事業を通じて、幼児から中高生、そして大人までを対象に自然体験の機会を提供。「アウトフィッター(自然や人との関わりの中で人生を前向きに生きている人)」の育成を掲げ、通年型プログラムやシーズンキャンプ、学校・企業向けプログラムを実施。お話:関口 千尋さん(本部事務局マネージャー)
▼NPO法人 国際自然大学校公式ホームページ
団体概要や、現在募集中のキャンププログラム詳細を確認することができます。
▼NPO法人 国際自然大学校国際自然大学校公式LINE登録ページ
国際自然大学校公式LINE登録ページです。追加すると、キャンプなどの最新情報が届きます。
▼NPO法人 国際自然大学校法人向けサイト
アウトドアのノウハウを活かした企業研修や福利厚生イベントにご興味のある方はぜひ!
秋は日帰りイベントや英語プログラム、冬休みにはスキープログラムなど楽しいイベントが盛りだくさんです。直近のプログラムはこちらからチェック!
文/羽田朋美(Neem Tree)