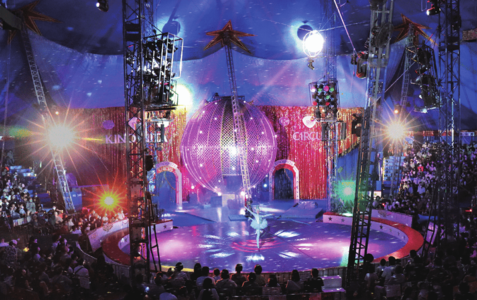「子育て四訓」から考える、子どもとの理想の距離感
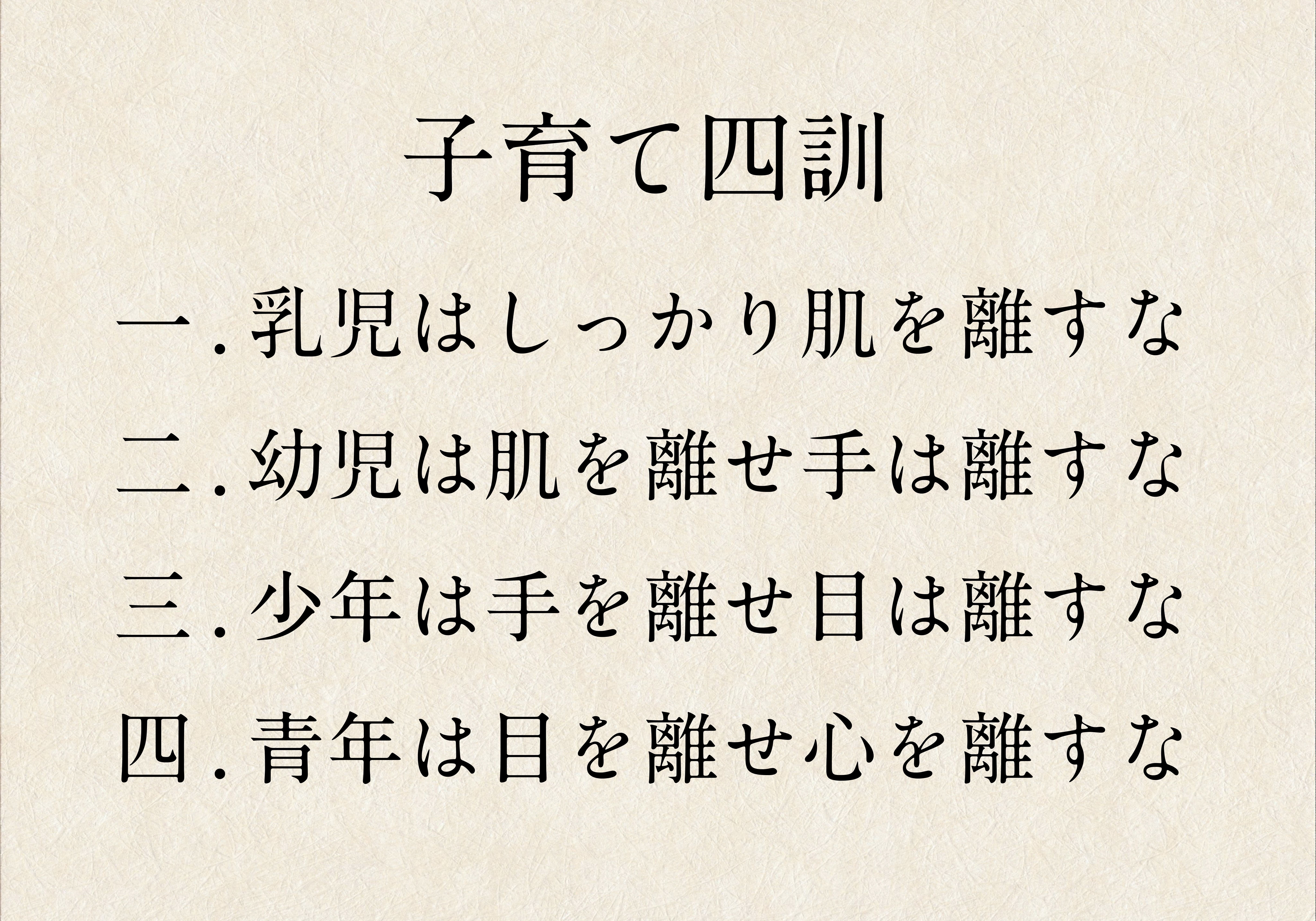
『子育て四訓』とは、山口県下関市の教育者である緒方甫(はじめ)先生が提唱した、子育ての心得です。
子どもはやがて親のもとを離れ、自立していくもの。この『子育て四訓』は、子どもの成長に応じて親が少しずつ距離を広げていくことの大切さを、シンプルで分かりやすい言葉で伝えています。
『子育て四訓』の意味を一つひとつ紐解きながら、パパママたちの実体験もあわせてご紹介します。
自分の子育ては、どの時期だろう?と振り返ってみるのもよいかもしれません。
一.乳児はしっかり肌を離すな

言葉でのコミュニケーションができない乳児期(0歳〜1歳頃)の赤ちゃんは、抱っこや授乳、肌と肌のふれあいによって親の愛情を感じ、心が安定する大切な時期です。この時期にたくさん触れ合うことで、親子の信頼関係が育まれます。
また、愛情をしっかり受け取った子どもは、将来的に自己肯定感が高くなり、良好な人間関係を築きやすいと言われています。
「乳児はしっかり肌を離すな」という言葉には、親子のスキンシップが最も重要なこの時期に、赤ちゃんの肌にしっかり触れ、愛情を伝えることの大切さが込められています。
<先輩パパママの声>
抱っこで寝かせたのに、布団に置くとまた泣き出して、結局また抱っこの繰り返し......。当時は『お願いだから寝て~!』という気持ちでいっぱいだった。でも、息子が成長し、思春期真っ只中の今は、ただただ懐かしく、いとおしい日々。もっとたくさん抱っこしておけばよかったな。もっと頬をすり寄せておけばよかったな......そんな思いがこみ上げてくる。(中2のママ)
ベビーカーが嫌いで、どこに行くにも抱っこだった息子。主人を亡くしたばかりで不安定だった私を気遣ってくれたのかな...抱っこすると自然と安心したことを思い出す。そんな息子も心の成長著しい青年期に。母も負けずに頑張ろうと思う。(中2のママ)
二.幼児は肌を離せ、手を離すな

幼児期(1歳〜6歳頃)は、興味や関心の対象が広がり、自分で動き回り、好奇心旺盛に世界を探検し始める時期です。赤ちゃんの頃のように常に抱っこする必要はありませんが、親の手のぬくもりを感じられる関わりが大切になります。
この時期は、自立心を育むためにも肌のふれあいは減らしつつ、子どもの手をしっかり握り、安全を確保しながら見守ることが大切です。
「幼児は肌を離せ、手を離すな」という言葉には、子どもの成長に合わせて少しずつ自立を促しながらも、必要な場面ではしっかりと支え、命を守ることの重要性を伝えるメッセージが込められています。
<先輩パパママの声>
タクシーを降りるとき、当時3歳だった娘が車道に飛び出し、危うく事故に遭いそうになったことがあった。ほんの一瞬の油断が、大きな危険につながると痛感。(小4、小1のパパ)
保育園に預け始めた1歳半頃のこと。甘えん坊の我が子は、毎朝、大泣きでのお別れだった。ずっと一緒にいた方がよいのかな...と悩む毎日、【肌を離せ、手を離すな】という言葉に救われた。保育園からの帰り道、手をつないで歩いたことが懐かしい。(大1のママ)
三.少年は手を離せ、目を離すな

少年期(6歳〜12歳頃)は、心身の発達が著しく、自立心が芽生えて親の手を借りずにできることが増えてくる時期です。親は手を離し、子ども自身に挑戦させることで、自信や責任感を育むことが重要になります。
しかし、この時期の子どもはまだ判断力が未熟で、無謀な行動を取ることもあります。手を離して自由にさせる一方で、決して放任せず、しっかりと目を離さずに見守ることが求められます。「少年は手を離せ、目を離すな」という言葉には、過度に干渉せずに子どもの自主性を尊重しながらも、親がしっかりと見守り、適切なサポートをすることの大切さが込められています。
<先輩パパママの声>
親の不在時に、子どもが電子レンジでボヤ騒ぎを起こしたことが。自分でできることは増えていくけれど、まだまだ危なっかしい部分もある。だからこそ、成長を信じて見守りながらも、日頃から安全に対する意識を育てることが大事だと感じた。(中1、小5のママ)
1年生、はじめてお友だちと遊ぶ約束をしてきた我が子。時間は決めたのに、場所を決めてこなかったとのこと...。近所の公園を二人で巡ったけれど、結局お友だちには会えず。トホホエピソードだが、失敗して学ぶことも多々あるのだと思った。(小2のママ)
四.青年は目を離せ、心を離すな

青年期(13歳〜18歳頃)は、親からの干渉を嫌い、自分の世界を持ち始める時期。親は過度に口出しせず、子どもを信じて見守ることが大切です。
しかし、「目を離せ」と言っても、完全に無関心になるわけではありません。最も大切なのは、心のつながりを保つこと。適度な距離を取りながらも、親はいつでも相談できる存在であることが、子どもにとって大きな支えになります。
「青年は目を離せ、心を離すな」という言葉には、子どもが自立するために、距離を置きつつも精神的なつながりを大切にして、助けが必要な時には支えられる存在でいることが重要というメッセージが込められています。
<先輩パパママの声>
息子が高校生のころ、ついつい口だしすぎては、ムッして部屋にこもってしまうことが続いて...。ぐっと我慢して、子どもの決めたことを尊重することに。そうしたら、息子から少しずつ、話してくれるように。子どもの成長に気づけていなかったと思う。(大1、高1のパパ)
進学で実家を出た息子。たまに通話アプリでスタンプを送ることで、さりげなく気にかけていることを伝えている。(大1、高2のママ)
今、この瞬間の関わり方が、未来の親子関係につながっていきます。子どもの自立を信じながらも、いつでも寄り添える存在であり続けること。それが、「子育て四訓」が伝えたい本当のメッセージなのかもしれません。
【関連記事】
▼小学生パパママ発!子どもの成長を感じてほっこりする瞬間
https://tama-tips.jp/living/blog/53-kodomo-seityo-episode.html
▼思わず笑っちゃう!子どもの無邪気なリアルエピソード
https://tama-tips.jp/living/blog/38-kodomo-episode.html
▼衝撃の数字に泣けてくる?子どもと過ごせる残り時間
https://tama-tips.jp/living/blog/5.html
取材・文/加賀美明子(NeemTree)